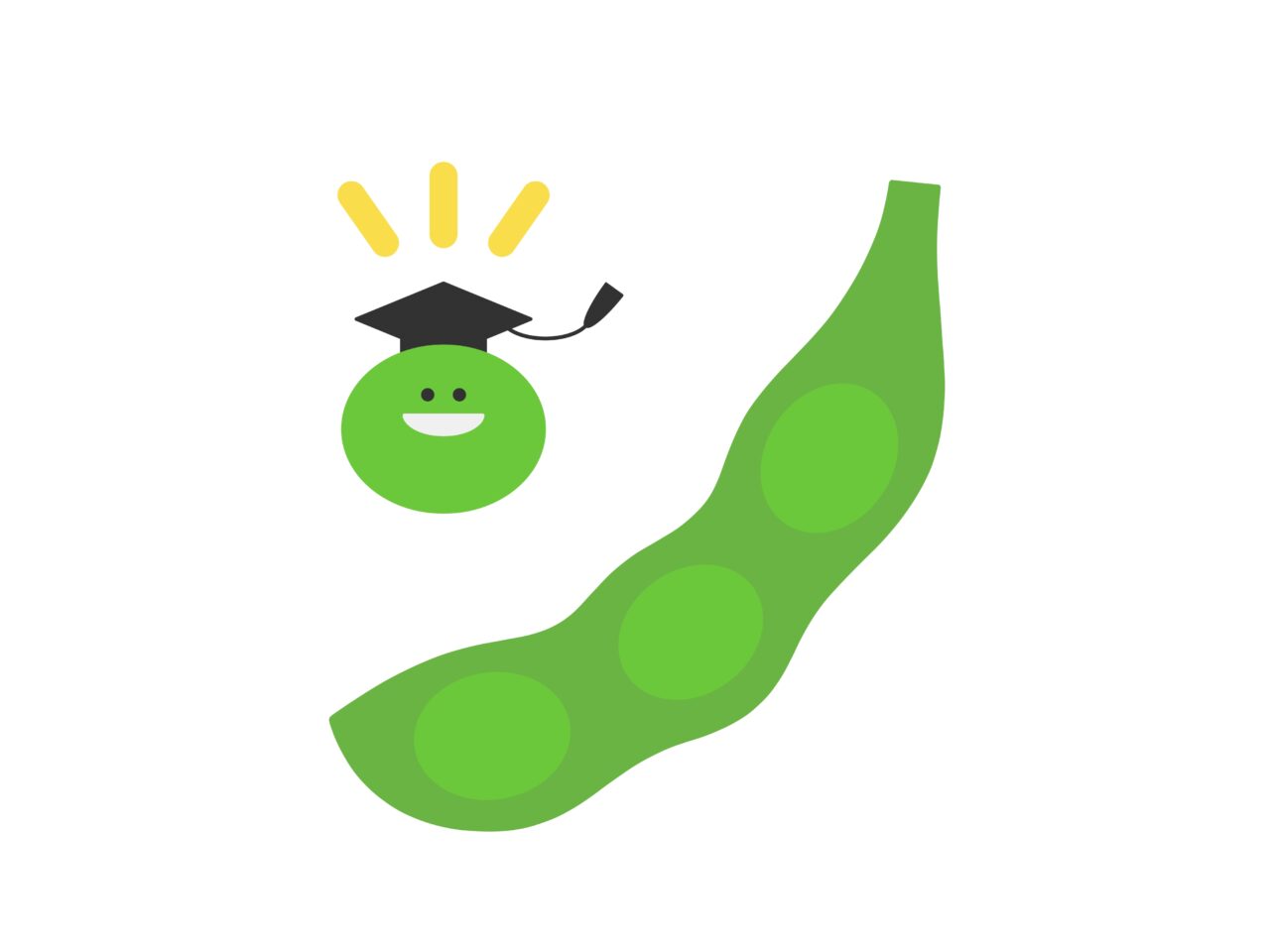同じ土地なのに広さが違う? ”面積”のいろいろ
こんにちは。サードブレインです。
不動産広告には、土地や建物の広さを表す用語がいくつかあります。
知っていると土地や建物を購入する際にイメージがしやすくなるので、ご紹介したいと思います。

1.“建築面積”・“延床面積”・“敷地面積”の違い
面積を表す用語には “建築面積”・“延床面積”・“敷地面積”があります。
“建築面積”とは、真上から見たときの建物の面積です。専門用語では“水平投影面積”といいます。
通常であれば1階部分の面積になりますが、1階より2階の方が広い場合は2階部分の面積が建築面積になることもあります。柱と屋根のある部分はすべて含まれますので、カーポートなども構造によっては建築面積に含まれます。また、“建ぺい率”を求めるときに用いられます。
“延床面積”は、建物の各フロアの床面積を足したものです。1階が40㎡・2階が60㎡の建物の延床面積は、100㎡になります。
この場合、単に各部屋の広さの合計ではなく、“壁芯面積”といって壁や柱の中心線で測った面積の合計なので、数字上では少し広くなります。また、“容積率”を求めるときに用いられます。
“敷地面積”は土地面積ともいわれ、その名の通り土地の広さです。厳密には土地を真上から見たときの“水平投影面積”で表します。このため、傾斜がある土地の場合は少し狭くなります。

2.“建ぺい率”と“容積率”
同じ広さの土地でも、決められた“建ぺい率”や“容積率”によって建てられる建物の大きさが異なります。
“建ぺい率”とは、敷地面積に対する建築面積の割合です。真上から見たときにどのくらいの大きさの建物が建てられるか、というものです。これは、安全性・快適性などを考慮して決められており、具体的な面積は計算式に当てはめればわかります。
敷地面積(㎡)×建ぺい率(%)=建築面積の上限(㎡)
例えば、敷地面積100㎡・建ぺい率50%の場合の建物面積の上限は、100㎡×50%=50㎡、敷地面積100㎡・建ぺい率80%の場合は、100㎡×80%=80㎡、となり、建ぺい率が高いほど広い建物を建てることができます。
“容積率”は、敷地面積に対して建てられる延床面積の割合です。床面積の合計によって何階建ての建物が建てられるかが決まります。こちらも計算式を見てみましょう。
敷地面積(㎡)×容積率(%)=延床面積の上限(㎡)
例えば、敷地面積100㎡・建ぺい率50%・容積率90%の場合は、建築面積の上限は50㎡・延床面積の上限は100㎡×90%=90㎡となり、1階が50㎡で2階が40㎡(延床面積の合計90㎡)の建物が建てられるということになります。
この計算式を知っていれば、売土地情報を見ただけで建築可能な建物の大きさのイメージができますね。
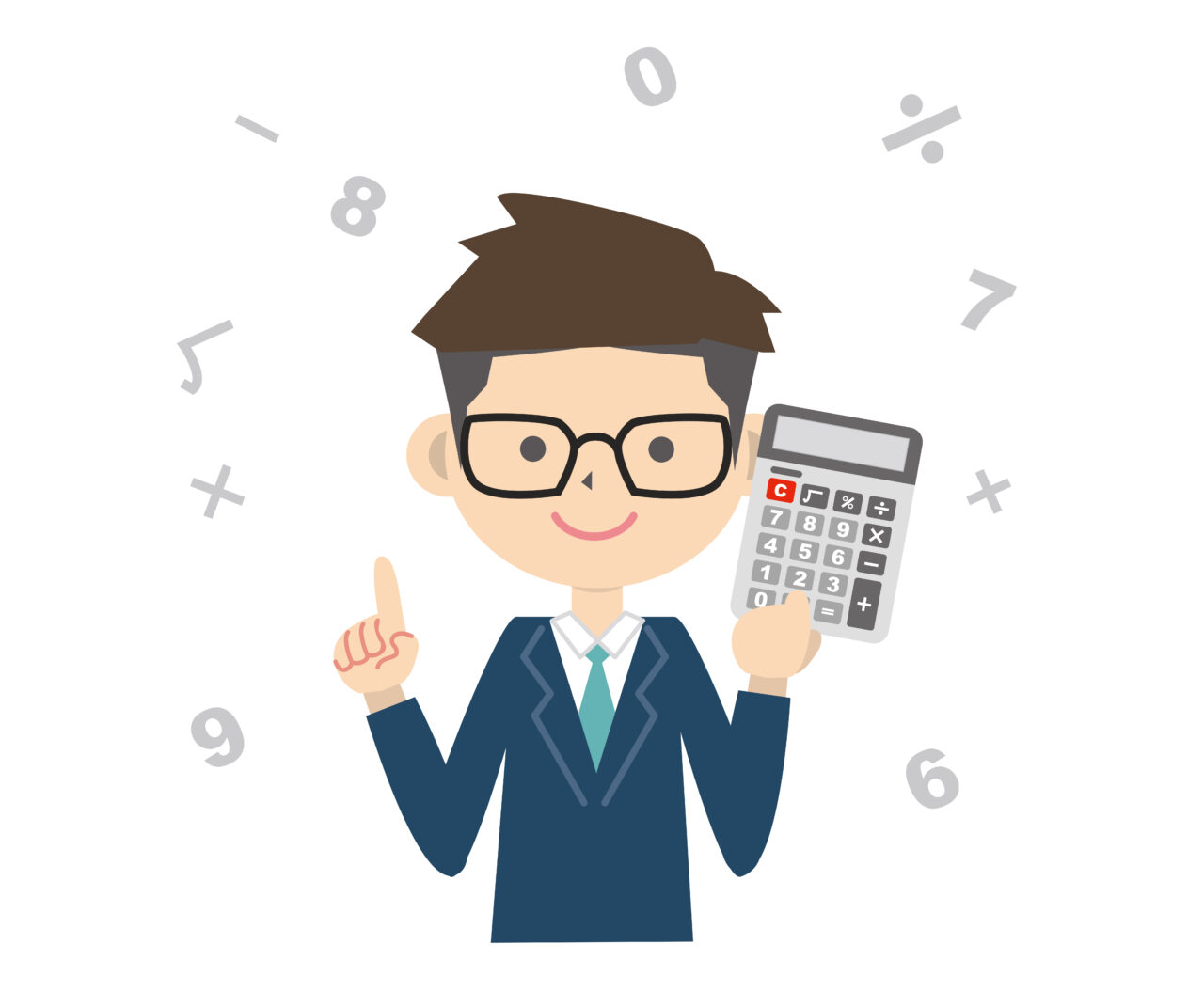
3.“建築面積”・“延床面積”に含まれるものと含まれないもの
“建ぺい率”や“容積率”で建物の大きさの上限が決まってしまい、希望通りの広い建物が建てられなくなるといったお悩みも少なくありません。
しかし、玄関ポーチ・ベランダ・バルコニー・出窓・地下室・吹き抜けなど、一定条件を満たすスペースは面積に含まれない場合もあります。“建築面積”と“延床面積”でそれぞれ条件が多少異なるので、詳しくは専門家にご相談ください。

この他にも、工務店やメーカーによって算出方法が異なる“施工面積”といったものもありますので、建物を建てられる際にはしっかり確認し、納得して住まいづくりを進めましょう。